
「映像の世紀 バタフライエフェクト 財宝と流転の人生」では、今回は清朝最後の皇帝・溥儀が取り上げられた。
溥儀が生き延びるために清朝の財宝を売ったり、常に自分を利用価値のある存在として見せなければならなかったというエピソードは、「権力を失った皇帝は、結局ただの一個人に過ぎない」という厳然たる事実を突きつけているように思える。
尾崎豊の『卒業』には、**「人は皆 縛られた か弱き子羊ならば、先生あなたは か弱き大人の代弁者なのか」**という歌詞があるが、このフレーズは、まるで溥儀を含む“時代に翻弄される人々”を指しているようにも感じられる。歴史の大きなうねりにさらされ、意志とは無関係に運命を変えられてしまう――そんな姿に興味と同時に哀感を覚えるのは自然なことだろう。
私が溥儀という人物を初めて知ったのは、ベルナルド・ベルトルッチ監督の映画『ラストエンペラー』だった。美しい映像美と壮大な物語が印象的で、二人の美しい妻に恵まれ、衣食住には困らない皇帝の暮らしぶりがまばゆく見えた。もっとも当時の私は、地方のスーパーで平社員として働きながら婚活も行き詰まっていた時期で、「人生の巡り合わせ」というものの不思議さを改めて考えさせられたことを今でもよく覚えている。
とはいえ、溥儀の生い立ちは決して幸福なばかりではなかった。紫禁城という閉鎖的な環境で育ち、外の世界をまったく知らないまま青年期を迎えた彼は、やがて西洋人の教師の影響を受け、紫禁城内の風習やシステムを近代化しようと試みたという。そうした改革への意欲は魅力的で、皇帝としての責任感を感じさせる。しかし当時の宮廷は宦官が実権を握り、腐敗が蔓延していた。小さな変化ではどうにもならないほど深く病んだ社会だったのだろう。
歴史をひもとくと、**「隆盛を極めた社会ほど、変化を拒めば自壊していく」**という摂理が見えてくる。清朝も、あるいは江戸時代の日本も、外圧や内部崩壊を契機に大きく変革せざるを得なかった。明治維新や太平洋戦争後のGHQ統治期のように、痛みを伴う改革が奇跡的な成長をもたらした一方で、既得権益の固定化や自己保身に傾くと、イノベーションは失速する。アメリカでは移民政策をめぐって対立が起きても、大学卒業式のスピーチで社会問題を堂々と批判する若者の姿が見られるなど、多様な意見がぶつかり合う活力が維持されている。この国なら、たとえAIバブルが崩壊しようとも、その躍動感ゆえに長期的な発展が期待できる、という思いから、私はS&P500への投資を続けているのだ。
番組の描き方については、溥儀を「臆病者で生にしがみつき、誇りを失った男」として強調していたように感じた。もちろん一理あるかもしれないが、近年のNHKの番組づくり全般に、ある種の政治的バイアスや“わかりやすい構図”に収斂させようとする傾向が見られるのではないか、と少々気になる。一方で、ウクライナ戦争や北朝鮮の問題などに目を向ければ、一筋縄ではいかない国際情勢の複雑さを思い知らされる。トランプが仲介に動けば状況が改善する可能性もあるが、犠牲となってきた兵士たちや市民の視点から考えれば、簡単に妥協はできないのだろう。そんなことを考えていると、放送の背後にある意図やメッセージを、受け手の私たちがしっかり読み解く必要性を痛感する。
結局のところ、溥儀の人生を振り返ることは、ただ“清朝最後の皇帝”という個人史を知るだけでなく、権力と社会の関係や、栄枯盛衰のサイクル、そして変革の必然性を再確認する作業なのだと思う。彼が辿った数奇な運命の足跡を追ううちに、私たちは、これから自分たちの社会がどう変化し、あるいは変化を拒んでいくのかを考えざるを得なくなる。歴史を“知る”という行為は、そのまま未来を“創る”きっかけでもある。そういう意味で、「映像の世紀 バタフライエフェクト」が投げかける問いは、決して他人事ではなく、今を生きる私たち一人ひとりへのメッセージなのかもしれない。

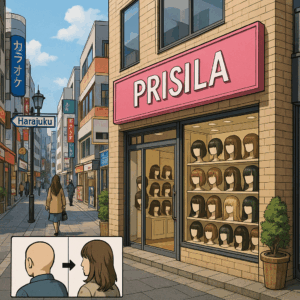
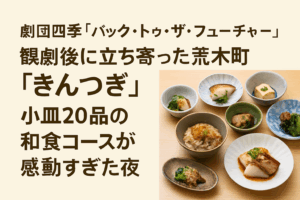
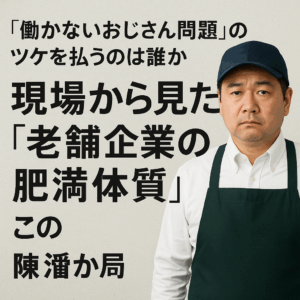
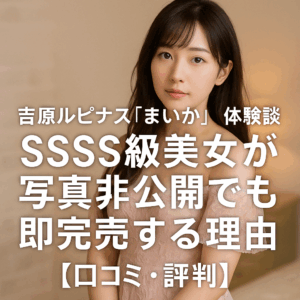

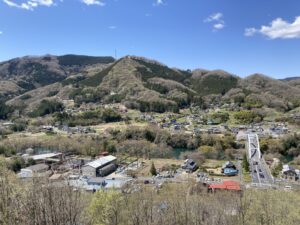


コメント