
― 劇的シーンとラブレターを描く挑戦 ―
島田雅彦氏が監修する通信講座「小説講座」にて、第7回の課題として提出した2作品(基礎編・応用編)を、全文掲載します。
あわせて、講師の方からいただいた添削コメントも全文公開いたします。
これから受講を検討している方や、創作に興味のある方にとって、実例として参考になれば幸いです。
■ 基礎編 『天使を引き当てた日』
課題テーマ:「誰もが一度は書きたくなる“劇的シーン”を原稿用紙5枚で描く」
▼ 作品全文
ゆっくりと瞼を押し開けると、淡く白い光が霞んだ視界に染みこんできた。目の前には薄いブルーのカーテンが垂れており、風もないのに時折ふわりと揺れている。病室特有の消毒液の匂いと洗いたてのシーツの香りが入り混じり、清潔さゆえにどこか不安を掻き立てる。壁際には金属製の点滴スタンドが静かに佇み、その横のモニター画面には規則的な波形が無機質に流れている。
やっとの思いで首を少し動かすと、枕元の小さなテーブルの上に花瓶が置かれていた。白いユリはまだ蕾のままで、差し込む日差しを浴びてほのかに輝いている。その隣にはストローの刺さった紙パックのお茶が無造作に置かれ、見覚えのないデザインの文字が印刷されている。
ふと視線を戻すと、ベッドの足元に二人の女性が立っていることに気がついた。一人は腕を組み、目尻に細かい皺を浮かべて静かにこちらを見つめている。もう一人はハンカチを手にして口元を押さえているが、その目元は笑顔とも涙ともつかない、不思議な表情を浮かべている。二人との距離はわずか数メートルのはずなのに、まるで薄いヴェールが隔てているかのようにぼんやりとしていた。
心臓が耳元で大きく鼓動を刻んでいる。私は何かを言おうと口を開いたが、喉が枯れきっているのか、息が漏れるだけで言葉にならない。
二人はゆっくりと、どこか戸惑ったような優しい表情で近づいてきた。
私は再び、渇いた口を精一杯動かして声を出そうとしたが、唇が微かに震えるばかりで、うまく声が出ない。何か普通ではないことが起きているのは、この身体の微かな震えで感じ取れた。
「わたしのこと、覚えている?」
先ほど目尻の皺が目立った女性が、さらに笑みを深め、顔を近づけて尋ねる。
私は必死で記憶を辿りながら、掠れた声でやっと絞り出した。
「おばあちゃん……だっけ?」
女性は目を潤ませながら首を振った。
「そうじゃないわ。……じゃあ、この人のことは?」
ハンカチを口元にあてている女性を指さした。
「あなたのお母さんよ」
二人の女性は視線を交わして、微笑を浮かべた。私は起き上がろうと身体に力を込めるが、口元以上に身体は言うことを聞かず、金縛りのようにまったく動かない。
やがて看護師が静かに入室し、私は椅子に乗せられて、隣接した小さな洗面室へと連れていかれた。看護師は無言で私に鏡を見せた。
「これは、誰だかわかりますか?」
鏡には精気を失った、見知らぬ中年の男が立っていた。目元には影が濃く刻まれ、かつての自分の面影を探すことは困難だった。私は無意識のうちに「これは私だ」と理解したものの、目に映る現実があまりにも突拍子もないため、心が受け入れようとしなかった。
「夢であってほしい」と願った瞬間、左腕に鋭く鈍い痛みが走った。視線を落とすと、点滴の管が透明なテープでしっかりと固定されている。その痛みと共に指先に伝わる微かな痺れは、逃れようのない現実そのものだった。
女性の一人がそっと私の手を握った。その手の温もり、乾いた肌の感触、細やかな震え――全てがあまりにも生々しく伝わってくる。
「夢ならば、こんなにはっきり感じるはずがない」
私は目を閉じて小さく呟き、自分が現実にいることを静かに悟った。底知れぬ孤独感と絶望が胸を締めつける一方で、その感情にはどこか懐かしささえあった。だが一夜にしてここまで自分の姿が変わってしまったことを、どう受け入れればよいのか、私にはわからなかった。やがて感情が溢れ、涙が頬をつたった。すると、ハンカチを持った年老いた女性が私の傍らに近づき、指で優しく涙を拭ってくれた。その指は震えていた。そしてゆっくりと顔を近づけると、私の頬に唇を重ねようとした。
私は驚き、無意識に口にしてしまった。
「あなたは、誰ですか……?」
まるで天使が私のために年老いた姿を借りて降りてきたかのような、淡い微笑を湛えながら、その女性は静かに答えた。
「あなたが結婚した相手ですよ」
■ 応用編 『封じられた想い、ほどける日』
課題テーマ:「ひとつのラブレターをめぐる、一人の男の三つの意識のありようを描いてみる」
▼ 作品全文
来月で定年退職を迎える私は、すでに年賀状のやりとりも整理しようと思い立ち、「今年限りにします」という旨のはがきを何人かに出しておいた。だから正月の朝、ポストを開けても特に何も届いていないだろうと思っていたのだが、一通の封筒がひらりと落ちたのを見つけて思わず息をのんだ。
宛名は私のフルネーム。けれど差出人の名はどこにも書かれていない。正月早々、こんなサプライズもあるのかと、どこか浮き立つような気分で封を切ってみると、折り畳まれた汚れの目立つ便箋に、懐かしい筆跡が飛び込んできた。若き日の私が書いたラブレター――しかも、小中学校が同級生だったあの女性に宛てたものだった。
なぜ四十年も経った今になって返送されたのか。引っ越しや家の取り壊し、あるいは誰かが昔の荷物を整理していて見つけたのかもしれない。彼女本人が送ったのか、それとも彼女の子どもが見つけて投函したのかもしれない――そんな想像が次々と浮かんでは消えていく。思わず胸が高鳴るのを感じながら、一字一句を眺めれば、当時の輝かしい記憶がまざまざとよみがえってきた。
海辺の写真を一緒に見てはしゃいだ夏がある。真っ青な海と白い砂浜を背に、彼女は銀色のヘアピンで前髪を留め、ほのかにレモンの香りが漂う髪をなびかせていた。ディズニーのシンデレラ城の前では、まるでプリンセスになったかのように無邪気に笑い、私の腕をとっては記念写真を撮ろうとねだる。白くなめらかな首筋や、涼やかな瞳、周囲を包み込むような優しさは、まさに“天使”と呼ぶにふさわしかった。私の愚かなほどの純粋さが、そんな彼女を余すところなく神聖視していたのかもしれない。
大学生になっても私たちの付き合いは続いていた。ところが就職を控えたある春の日、彼女は突然「もっと広い世界を見たいの」と言い、涙をこぼしながら走り去っていった。その言葉が、私にとって最後の記憶。いったい何が彼女をあそこまで突き動かしたのか分からぬまま、私はただ立ち尽くした。メールや電話はことごとく無視され、友人としての付き合いさえも叶わないまま、時は容赦なく過ぎていった。十年ほど経って彼女の結婚の噂を聞いたときは、心がずしりと沈むのを感じた。私の中では、あの天使のような微笑みだけが、暗い闇の中にぽつんと取り残されたように輝いていた。
後に、むなしくなって足を運んだ風俗店で、外見の美しい女性を抱いたことがある。けれどその女性の口臭があまりにきつく、衝撃を受けた。人は外面だけでは分からない毒をどこかに抱えているのではないか――そんな屈折した観念が私を苛んだ。あの女性も、結局は同じように冷たい暗部を持っていたのかもしれない……そう思い始めると、かつての熱烈な恋心はいつしか憎しみにも似た黒い塊に変わっていった。
そんな私の邪推をあざ笑うかのように、ふと知人づてに聞きかじった話やFacebookの断片からは、まったく別の姿が浮かび上がる。彼女には二人の子どもがいて、そのうちの一人は障がいを抱えているらしい。離婚を経験し、シングルマザーとなった彼女が、ヨーグルトを指につけて壁に絵を描こうとするわが子を、ただ優しい眼差しで見つめている写真を投稿していたという。そこには、私が憶測していたような冷たい暗部など微塵も感じられない。むしろ、あの頃と変わらぬ純粋な愛情の輝きがあった。
だとしたら、なぜ彼女はあのとき突然私の前から去ったのか。人生には人それぞれ、他者には決して測れない事情や迷いがあるのだろうと、定年を迎える今になって思い至る。傷ついたのは私だけだと信じていたが、もしかすると彼女のほうも苦しんでいたのかもしれない。
手紙に目を戻すと、若き自分の精一杯の言葉が詰め込まれている。まっすぐで、どこまでも純情な愛の表白。それを、四十年という歳月を経て今、こうして再び手にしているという不思議。胸の奥底から、遠い追憶の光が溶けだすのを感じる。憎しみや恨みは、すべて私自身が作り出した影だったのだろう。もう一度会って、同じように笑い合える日は来るのだろうか。あるいは、このまま生涯を終えるとき、せめて一言でも言葉を交わしたいものだ。
ひとしきり涙がにじんだあと、私は手紙をそっと封筒に戻す。海辺で彼女が見せたまぶしい笑顔、夢の城を見上げてはしゃいだ遠い夏の日――あのとき、私があの人を愛していたことは揺るぎない事実だし、それが私の人生を決定的に彩ってくれたことも確かなのだ。
そう思うと、不思議なくらい心が軽くなった。天使なんていないと嘲笑する自分もいれば、いや天使はいるのだと信じたい自分もいる。どちらも私だ。瞼を閉じれば、いまだに彼女の面影が郷愁のように浮かんでくる。
大和田知里――その名前をそっと胸の中でつぶやくと、別れの痛みさえも懐かしく思えてきた。
▼ 講師添削コメント(全文)
基礎編の課題『誰もが一度は書きたくなる、「劇的シーン」』、応用編の課題『ひとつのラブレターをめぐる、一人の男の、三つの意識のありようを描いてみる』をお送りいただきありがとうございます。
まず基礎編『天使を引き当てた日』ですが、文章力も上がっていて、テーマと相まって切なさややるせなさも伝わってきました。20年ぶりに目覚めた主人公の戸惑いもよく書けていたと思います。20年ぶりに目覚めて、妻と母と向き合う主人公。それをnyoraikunは切なくも美しく書いていました。
ラストの妻のセリフも、絶望の中に一縷の望みが垣間見えて、失われた年月の重さと、今後も連れ添って生きていくという覚悟が伝わってきました。セリフで締めたのは、今作において効果的だったと思います。
2020年に日本テレビで放映された『35歳の少女』というドラマはご存知でしょうか。主人公は10歳の時に交通事故に遭い、以後25年間意識不明でした。やがて35歳で目覚めるのですが、彼女の目から見る世界は10歳の頃とは一変しているのです。両親は離婚、頼もしかった父親は別の家庭を持ち会社をリストラされ現在は無職、やさしかった母親はすっかり老け込んで気難しい性格に変貌、可愛い妹は家族を顧みずひねくれ三昧、とこんな感じです。
今作の場合、察するに主人公は20代~30代から20年間昏睡状態だったのですよね。20代~30代から40代~50代の変化は10歳から35歳の変化よりは激しくないかもしれません(男性と女性で立場も違いますし)。とはいえ、身体感覚のズレ(脳の指令どおりに身体が動かない)というのもありそうですよね。そう、感覚としての老いです。主人公の戸惑いや悲しみなどは真に迫って、心情として書かれているのですが、身体的にはどうだったのでしょうか。
見た目ではなく、関節の動きなど、目や耳の感覚等です。そういう体感的な描写を作家目線でリアルに描いていくと、説得力が増します。それと今作では具体的に「20年」という月日が書かれていないのが気になりました。後半で「だが一夜にしてここまで自分の姿が変わってしまったことを、どう受け入れればよいのか、私にはわからなかった」とありますので、読者は主人公が一夜にして老いてしまった、と思い込むでしょう。
今作は課題なので、課題を知っている講師しか読まない、というのが前提ですが、課題であれ何であれ初見の読者が読む、という前提で書いてほしいです。 いろいろと難癖をつけていますが、劇的シーンを原稿用紙5枚で書く、という課題自体が高度なのです。手厳しいことを指摘しているのは私も承知しております。が、とりあえず念頭に置いてみてください。
応用編の『封じられた想い ほどける日』は、かつてすれ違ってしまった男女の関係と、男性側の未練や思い出の美しさがうまく描かれていたと思います。文章や表現力(基礎編同様)も巧みでしたが、ちょっと表現が過剰でモノローグが多く、動きがないのが(心の動きではなく身体的な動き)気になりました。
課題である、一人の男(主人公)の三つの意識のありよう、というのは書かれているのですが、主人公の感情重視で、細かな設定がおろそかになっているのも、一読者としてモヤモヤが残ってしまったのです。まずなぜ彼女は去って行ったのか、その理由は解明すべきです。いわゆる伏線の役割をしているので、伏線は解消しなくては読者はカタルシスを得られませんよね。さらに主人公は現在既婚なのか独身なのか、妻はいるのか別れたのか、といった背景も知りたいです。背景によってはこのラブレターが波乱を呼ぶことになるからです。
波乱を呼べば物語に動きが出ますし、波乱を呼ばないにしても、既婚か独身かでかつての感情と現在の感情を比較しやすくなりますし、主人公の心情にも厚みが出ます。あとはラブレターの出所をはっきりさせてほしかったです。 応用編の重要な小道具は、言わずもがなラブレターです。受講生の中には、テーマでもある小道具の手紙の存在を疎かにしてしまう方は割といました。
皆さん、「不思議なこともあるものだ」とか「どうして今になってこれが届いたのだろう。不思議に思いながらも私は……」とか、主人公自身が問題を曖昧にしてしまい(そのまま作者の意思みたいに思えます)、話を先に進めてしまうのです。しかしやはり、細かい点だとしても(いえ、細かい点だからこそ)、読者が疑問に思う点は改善しなければいけないのです。しかも今作の肝である手紙が曖昧な扱いをされると、一気にリアリティが削がれてしまいます。 第8回の課題も高度です。でも高度だからこそ、得るものも大きいと思います。 次回の課題も楽しみにしております。
■ おわりに
「小説講座」の課題を通じて、“読者に伝わる物語とは何か”を自分自身に問い直すことができました。
どんなに情熱を込めて書いたとしても、それが「伝わらなければ届かない」。添削を通じてそのことを実感しました。
これから受講を検討している方へ――ぜひ一度、自分の限界を知るためにも、小説講座という“鏡”の中に作品を投じてみてください。



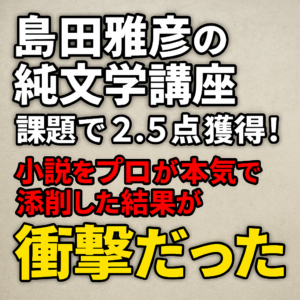
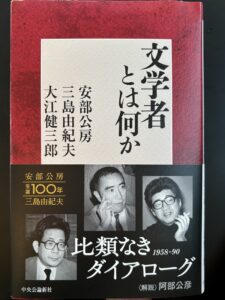
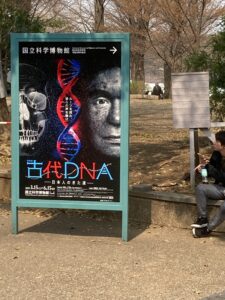


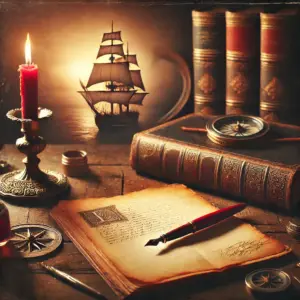
コメント