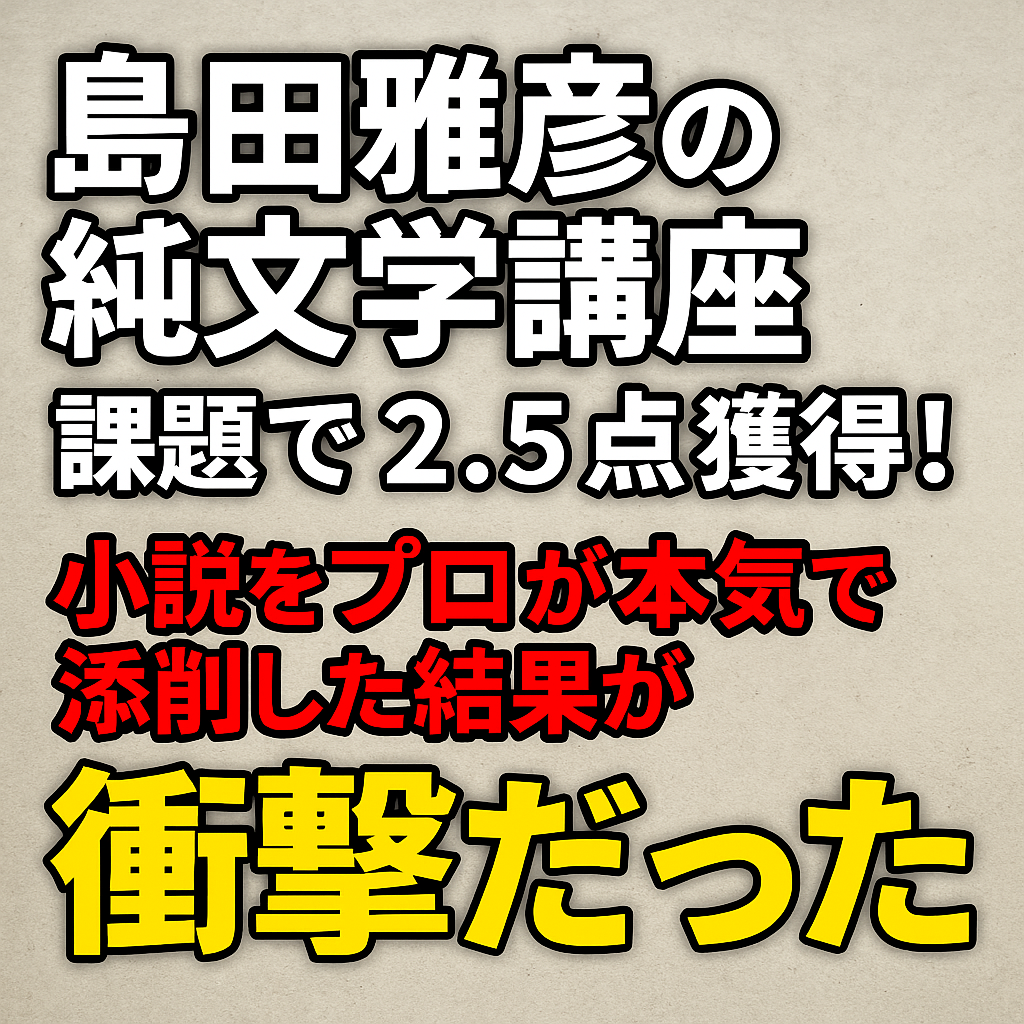
【島田雅彦の純文学講座 課題受領7】
nyoraikun様
基礎編:2.5点(3点満点) 応用編:2.5点(3点満点)
基礎編の課題『たったいま、座っている場所を描写してみる』と、応用編の課題『行ったことのない場所をひとつ設定し、資料を使って描写してみる』をお送りいただきありがとうございます。
まず基礎編『扉が開くたび』についてですが、どこか他人行儀な(褒めています)硬質な文章で、淡々と部屋の様子が伝えられています。描写という課題に対して実に遜色のない文章で、その冷たさ(褒めています)が少々気にはなったものの、終盤に近づくにつれ両親への思いや老いに対する切なさが匂い立ち、しみじみとさせられました。主観と客観のバランスが見事でした。
基礎編の課題は『たったいま、座っている場所を描写してみる』ですので、今作は満点に近い出来です。ではなぜ0.5点を欠いたかというと、情景描写を心理描写につなげてほしかったからです。
例えば、中盤で「ふと鼻腔をくすぐるコーンクリームスープの匂いに気づいた。」とありますよね(細かいですが、言い回しが少々まどろっこしいです。「コーンクリームスープの匂いが鼻孔をくすぐった。」で良いと思います)。しかし、両親は主人公のために特上寿司を用意するのです。コーンクリームスープとお寿司はどう考えても合いません(「めっちゃ合うよ!」という意見でしたらすいません)。このちぐはぐな感じをジェネレーションギャップあるいは思考の食い違いとして心理描写につなげられるはずなのです。そして、年齢差は変わらないはずなのに立場や考え方がかけ離れてしまった両親を切なく思う、というふうにつなげられるでしょう。
情景描写を心理描写につなげる、または小道具を心理描写につなげるという表現方法は、小説ならではの技術ですので、ぜひここで習得してほしいです。現状のままでも主人公の切なさは伝わってきますが、情景や小道具に心理を投影させると、より一層リアルに読者の心に刺さります。
応用編『お歯黒溝の向こうへ』ですが、こちらも基礎編同様、とても上質な文章で的確に書かれていました。基礎編とはうって変わって情緒的な雰囲気でしたが、硬質な文章に包まれた切なさは健在で、nyoraikunさんの手札の多さに驚いた次第です。情景も無理なく浮かんできて、色とりどりであるはずの吉原の、しかしどこかくすんだ味わいもよく表現できていると思いました。悲しき歴史の一端であるはずの吉原ですが、今作を読み、過去のその場所に行ってみたくなりました(行ってみたくなる、というのはシンプルですが、紀行小説にとって一番の誉め言葉だと思っています)。
ただ応用編のほうは情景描写がやや少なく、モノローグ主体で進んでいったのが惜しいです。文章力もありますし(今回文章力が飛躍的に伸びたのを感じています)、読んでいて胸に迫ってくるような主人公の感情も素晴らしいのですが、応用編の課題『行ったことのない場所をひとつ設定し、資料を使って描写してみる』における「資料を使って描写してみる」が少々足りていないように思います。もう少し、当時の吉原をnyoraikunさんの筆で描写してほしかったです。
今回の課題で特筆すべき箇所は、基礎編では「たったいま」、応用編では「行ったことのない」という部分です。「たったいま」というのはかなり限定されていますし(狭い範囲ですよね。たったいま座っている場所というのは、イス、畳、絨毯、床……何にしても半径1メートルもありません)。また「行ったことのない場所」ですが、作者が行ったことがなくても小説の主人公にとっては「行ったことがある」あるいは「今、初めて訪ねた」という設定になりますよね。ですから読者にその場所を伝えるためには、その場所の空気感を描かねばならないのです。
作者自身は行ったことがないのに空気感を書けというのも、いささか無理な話です。しかし、その無理を承知でやるのが小説なのです。基礎編では観察眼が(自分がいる場所の半径1メートルを描写し、心情につなげ、小説として昇華させるということです)、応用編では想像力が(行ったことのない場所の空気感をリアリティをもって読者に伝えるということです)、それぞれ養われ鍛えられます。
今までのどの課題も勉強になりますが、今回の課題も非常に勉強になります(私も勉強させてもらっています)。
次回の課題も楽しみにしております。
基礎編『扉をひらくたびに』
外に目をやると、冬の夕暮れが静かに町を包み込みはじめていた。半径一キロメートルほど先にあるショッピングモールの屋上看板が、冷たい空気に霞んでいる。風が弱い分、空は澄み渡り、遠くの山並みが薄紫色に沈む。窓ガラスを通して伝わる冷気に、手をこすり合わせながら部屋の中に視線を戻した。
高校生の頃からほとんど変わらない、自分だけの空間。四畳半の狭い部屋は整然としているが、机の上だけは雑多だ。右隅には鮮魚の仕事関係の書類が積まれ、左手にはマッドデスクシートに挟まれたGoogleアドセンスの個人識別番号通知書がある。収益化にはあと二千円ほど届かないまま、入力の機会も与えられず放置されたPINコードは、印刷されたまま色褪せずに残っている。
シートには、原稿用紙の使い方や二重かぎかっこ、アラビア数字の表記方法などの基礎ルールがびっしり書かれている。実際に書き始めると、それらの知識はすぐに霧散し、迷いが生じるから不思議だ。画面を見つめてはキーボードに触れる指の動き。そのわずかなタイムラグさえも、今の自分にはもどかしい。
突然、隣の部屋からテレビの爆音が響いてきた。思わず肩をすくめる。母は耳が遠くなって久しいが、それを認めたがらず、いつも「テレビが壊れている」と文句を言う。先日、父が新しいものに買い替えたが、当然ボリュームの大きさは変わらない。外まで漏れていないかと心配になるほどだが、母本人は意に介さないらしい。
扉が少しだけ開いて、父が顔を出した。「洗濯物、ちょっとかけに来たぞ」。テレビの音がさらに流れ込み、耳をふさぎたくなる。父は干し終わると、こちらをちらりと見る。そのときの大きな瞳に、九十歳を迎えた人間の静かな気迫を感じる。「体、大丈夫か」と言いたげな空気を残して、扉を閉めた。
しんとした余韻は一瞬で途切れ、また数分後に父は寝巻きをハンガーにかけるため、同じように扉を開ける。今度は勢いよく「ガチャン」と締められ、妙な振動が胸に残った。何度も繰り返される扉の開閉に、落ち着かない気分を抱えながら、私はまたキーボードを打つ。
ふと鼻腔をくすぐるコーンクリームスープの匂いに気づいた。そろそろ夕食の時間らしい。きっと今日も、父と母は私にだけ特上寿司を用意しているのだろう。自分の老後への不安を誰に託せばいいのか、あの二人なりに考えているのかもしれない。ありがたい気持ちと、後ろめたさが入り交じる。いずれ介護が必要になるとき、自分は両親を本当に愛せるのだろうか。そんな疑問が、寒い夜の空気のように胸に刺さる。
窓の外を見やる。駅へ続く道の街灯がともり始め、赤く染まった雲がゆっくりと流れていた。半径五十メートルほど先には小学校があるが、もう児童の声は聞こえない。ひとしきりざわめいた世界が、日没とともに一度息を潜めるかのようだ。それでも家の中はまだ騒がしい。テレビの音と、台所の湯気の立つ匂いが混ざりあい、ここに暮らす人々の時間をしっかりと刻んでいる。
そんな雑踏の真ん中で、私はパソコン画面を凝視しながら、また迷う。書きたいことも描かなくてはならない現実も、目の前に山積しているはずなのに、指は思うように動かない。ふと机上のPINコードに視線を戻し、かすかな苦笑を漏らす。二千円の差はいつか埋まるのだろうか。そして両親との溝もまた、何かの拍子にさらりと埋まってくれるのだろうか。そんな期待を抱くのは、あまりに甘いかもしれない。
それでも、カーテンの隙間から射し込む残照は、デスク上の散らかった紙やシートをほんのりと照らしていた。小さな光の帯が、私の部屋をかすかに彩る。部屋の外、さらに広い世界へと思いをはせながら、私はもう一度、キーボードに手を置く。玄関先で父が呼ぶ声がした。ドアを開ければ、夜が本格的に始まる時間だ。私は席を立ち、食卓へ向かう。テレビの大きな音が耳を打つたび、これもまた、消えゆくことのない日常の一部なのだと実感する。
応用編『お歯黒溝の向こうへ』
風がない夜だった。
障子の隙間から覗く空は、墨を流したように重たく、月は厚い雲の向こうに隠れている。
この塀の外にも、同じ夜があるのだろうか。
紅葉は、ぼんやりと座敷の畳に指先を滑らせた。
畳は、何度も何度も踏みしめられ、磨き上げられ、肌に馴染むほどに滑らかだった。だが、外の風を知らぬそれは、まるで籠の中の鳥の止まり木のようでもあった。
吉原の塀は高い。
昼になれば、大門はぴたりと閉ざされ、女たちはどこへも行けない。夜になれば、外からは大勢の男たちがやってくるが、女たちはやはりどこへも行けない。
紅葉がこの遊郭に売られてから、もう何年経っただろう。
どれほどの男を相手にしても、どれほどの客に夢を見せても、この塀の外へ出られるわけではない。
ときおり、遠くから微かに聞こえるのは、吉原を囲む「お歯黒溝(おはぐろどぶ)」を流れる水の音だ。雨が降るたびに、溝は黒く濁り、遊郭の内外を隔てる見えぬ境界線となる。
——あの水がどこへ流れていくのか、知る者はいない。
と、どこからか微かな笑い声が聞こえた。
男の笑い声と、女の甘えた声。
すぐそばの座敷で、誰かが客をもてなしているのだろう。
その声の向こうで、紅葉はふと、遠くを歩く足音を聞いた気がした。いや、気のせいかもしれない。ここでは、外の音など聞こえるはずがないのだから。
「姐さん」
襖の向こうから、禿(かむろ)の少女の声がした。
「今夜のお客が来たよ」
紅葉はゆっくりと、唇を結んだ。見えない夜空を仰ぎ、静かに目を伏せる。紅葉は襖の前で小さく息を吐いた。
指先を袖に滑らせ、朱の爪先を隠す。表の帳場では、遣り手婆が客と話している声がする。
「旦那、紅葉は今宵も機嫌がよござんすよ」
嘘だ、と紅葉は思った。
襖が開く。
客が入るのを待つ間に、紅葉は瞬きもせず、伏せたまつげの裏で想像をめぐらせた。
今宵はどんな男か。上等な商人か、それとも田舎侍か。それとも、金を溜め込んだ町医者か。
——いや。そのどれでもない。
帳場で聞こえた声の主が、座敷へ足を踏み入れたとき、紅葉はわずかに目を上げた。
その男の足音には、どこか奇妙な静けさがあった。まるで影が歩くような、軽やかで、けれど決して軽薄ではない響き。
「お初にお目にかかります」
男はすっと座し、軽く膝を折ると、にじり寄るでもなく、紅葉との間に適度な距離を保った。
——武士か。
紅葉は直感した。男は三十がらみだろうか。頬がやや痩け、顎のあたりに無精髭が残っている。身なりは簡素で、しかし着崩したところがない。遊郭の常連たちとは違う、妙な清廉さがあった。
「今宵は、貴女とゆるりと話がしたくて参りました」
男は静かにそう言った。
その声は、まるで塀の外から聞こえてくるような響きを帯びていた。
紅葉は微かに首を傾げる。
話? ただ話をするために、わざわざここへ?
「珍しいお人だこと」
扇を開き、口元を隠しながら微笑む。
「皆様、紅葉には夢を見にいらっしゃるもの。ただお話がしたいとおっしゃるのは、風変わりなお方ですわ」
男はふっと唇の端を持ち上げた。
「夢を見に来たのは、むしろ私ではなく、貴女の方では?」
——夢?
紅葉の微笑が、わずかに凍りつく。
「私の方が?」
「貴女は、この塀の向こうへ行きたがっているのではないか」
静かに、だが確信に満ちた声音だった。紅葉の指が、一瞬だけ震える。男は何者だ? どうしてそんなことを——。扇の陰で、じっと男の目を窺う。
この男は、ただの客ではない


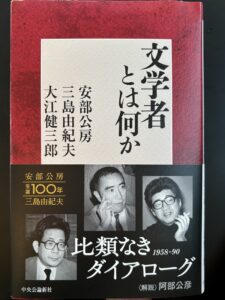
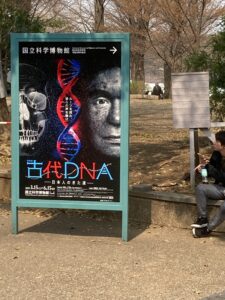


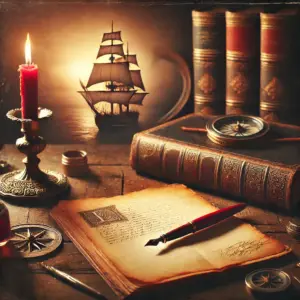


コメント