
会話だけの小説を原稿用紙3枚で書くというもの。
小説講座に送った原稿
「久しぶりに来たけれど、このバーも随分と様変わりしたね。まるで、古い夢の続きを見ているようだ。」
「ええ、前より静かで、どこか無機質になったわね。まるで時間が止まったみたい。」
「いや、変わったのはバーじゃない。俺たち自身が少しずつ変わってしまったんだろう。昔のように騒ぐのは、もう似合わなくなったかもしれないな。」
「かもしれないわね。でも、こうして静かに話せるのも悪くない。今夜も、まだ終わらない何かが漂っている気がするわ。」
「終わらない、か。あの夜の余韻が、まだここに残っているのかもしれないな。まるで何かの影が付きまとっているような感じだ。」
「影の話はやめて。誰かに聞かれたら、全部が消えてしまうわ。そういうのは、胸の奥にそっと仕舞っておくべきでしょ。」
「そうだな。わかっているさ。バラすのは無粋というものだ。」
「でも、面白かったじゃない?あの瞬間、誰もが普段の自分とは別の人間に変わったみたいで、妙に刺激的だったわ。」
「刺激的ね…。確かに、あんな風に誰もが知らない表情を見せるとは思わなかった。まるで仮面を剥がされたような。」
「普段見せない顔が見えるのって、不思議な感じがするのよね。まるで鏡の中で見たことのない自分と向き合っているような。」
「君もね。普段は冷静なくせに、あの時の君の目つきが忘れられない。まるで別の生き物のようだった。」
「ふふ、そういうのは心に飲み込んでおいてよ。俺だって、たまには自分を壊してみたくなる時があるんだ。」
「壊れることね…。壊れることでしか得られない感覚があるのかもしれないわ。日常にはない、特別な。」
「そうだ。だからこそ、またこうして集まりたくなる。次の予定も考えなきゃいけないだろう。」
「準備がいいのね。でも、次はもっと深い場所がいいわ。誰にも知られず、もっと遠くで。」
「そうだな。もっとクローズドで、外の世界とは完全に切り離された場所。誰にも見つからないように。」
「そう、誰にも知られずに。それが一番心地いい。誰かに見られることなく、ただ自分だけの時間。」
「じゃあ、次の夜も決まりだな。また俺たちだけの秘密が、あの闇に潜む。」
「秘密…そうね。また次の夜が楽しみになるわ。誰にも言えない、あの瞬間の続きが待ってる。」
「次はもっと大胆にいこう。誰がどんな顔を見せるか、次の幕が楽しみだな。」
「今夜はこれで終わりにしよう。また次に会う時まで、この余韻を味わいながら。」
「じゃあ、次の夜に乾杯だ。俺たちだけが知っている、あの続きを。」
「誰にも話さない。あの時も、これからのことも。全て、俺たちだけの夜だ。」
講評
nyoraikun 様
基礎編3点(満点)
応用編2点(3点満点)
基礎編の課題『ふだんの生活では絶対に行かない場所に行き、そこで交わされる会話をメモする』と、応用編の課題『4名の登場人物が集合して話し合うシーン』を、お送りいただきありがとうございます。5回目の課題で、純文学講座もほぼ折り返し地点です。課題をこなしていく中で、何か学んだ実感を得られましたでしょうか。やはり小説は難しいと凹んだり、あるいはさらに奮い立ったりしたでしょうか。
第5回の基礎編の課題は文字通り『受講者がふだんの生活では絶対に行かない場所に行き、そこで交わされる会話をメモする』ということです。つまり創作ではありません。nyoraikunが実際に何処ぞへ赴き、人々の会話を盗み聞きしてメモする、というのが正解です。コロナ禍の頃は、受講生の皆さんはテレビやラジオ、あるいはYouTubeを活用するなど工夫を凝らしていました。この工夫を凝らすというのも創作の一環になります。素晴らしいと私のほうが感心させられました。
nyoraikunが選んだのは新橋の立ち飲み屋です。メンバーは、中年のサラリーマンA、B、新入社員の若いサラリーマンC、他にアルバイトの女性店員1名です。仕事を離れてくつろぐ時間、しかもお酒が入ると人は無防備になります。理性や虚勢という殻にヒビが入るのも決して珍しくないですよね。そんな雰囲気の中で交わされる会話を盗み聞きして、nyoraikunはどう思ったでしょうか。
一見、かみ合っているようでかみ合っていない、意味が通じているようで通じていない、傍目から見て(聞いて)人々の会話はわりといい加減なんだな、と思いませんでしたか。このいい加減さというのは、ユーモア感覚につながります。
さて応用編『静かな夜の秘密』です。こちらは隠れ家的なバーですね。ところでこちらは男女のふたりが会話しているようですが、課題は4人となっています。課題から逸れてしまったという点でマイナスなのですが、会話そのものはなかなか洒落ていました。ただ、言ってしまえば雰囲気だけが十分な会話で、結局読者にはふたりが何を言い合っているのかよくわからないのです。謎めいたことを言い合って、お酒を飲みながら、こちらもなんとなくいい雰囲気を味わうのですが、その実、この話はどこにつながるのか? あるいは、この話は一体何を言っているんだ? という疑問を残したまま終わってしまいます。影とはいったい何なのか、このふたりの関係は何なのか、他のメンバーとはどういった関係なのか?秘密結社なのか?と、腑に落ちないモヤモヤが残ってしまうのです。
さて、会話だけを羅列するという書き方に不安を覚えた受講生もいたようですが、nyoraikunはいかがでしたか。地の文が書けないとなると、嫌でもセリフに工夫をしなければならなくなりますよね。ここが不安ポイントというか苦手ポイントとなるのですが、裏を返せばかなりの学びポイントになります。セリフだけで登場人物の区別をつけなくてはならないのですから、どうしたって頭をひねらなくてはならないのです。では、地の文がなく会話だけをつなげる、という課題の意図するものは何でしょうか。セリフに個性を持たせることです。セリフだけで登場人物の性格や職業、立場などを表現するのは難しいのです。ついつい説明口調になってしまいますし、地の文がなく会話だけで原稿用紙3枚、となると意外に長くて大変です。
第5回の課題は実によくできていて、基礎編から応用編にいくと、会話文の難しさや使い方がつぶさにわかってくるようになるのです。会話は通常、地の文がないと誰が誰だかわからなくなってしまいますよね。そこで読者にわかってもらうためのテクニックが、自然とついてくるのです(なので、基礎編も登場人物の名前をセリフの前に書かないほうが学びになりました)。受講生の中には方言や訛りを使ってみたり、語尾を変えてみたり、登場人物の個性を出すべく工夫されている方もいました。
小説は読者の心を揺さぶり、楽しませるものです。作者は読者の想像の上を行き、良い意味で読者を裏切らなければなりません。
次回の課題も楽しみにしております。

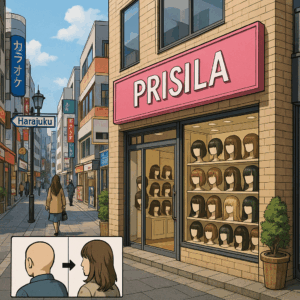
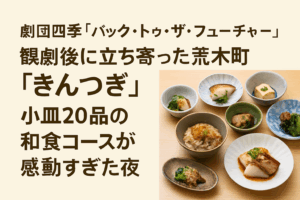

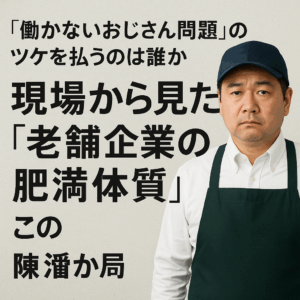
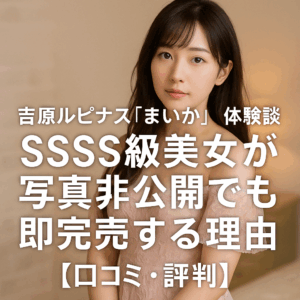

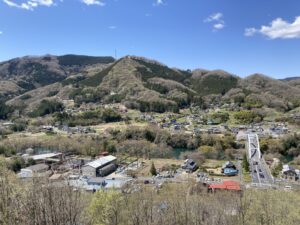

コメント