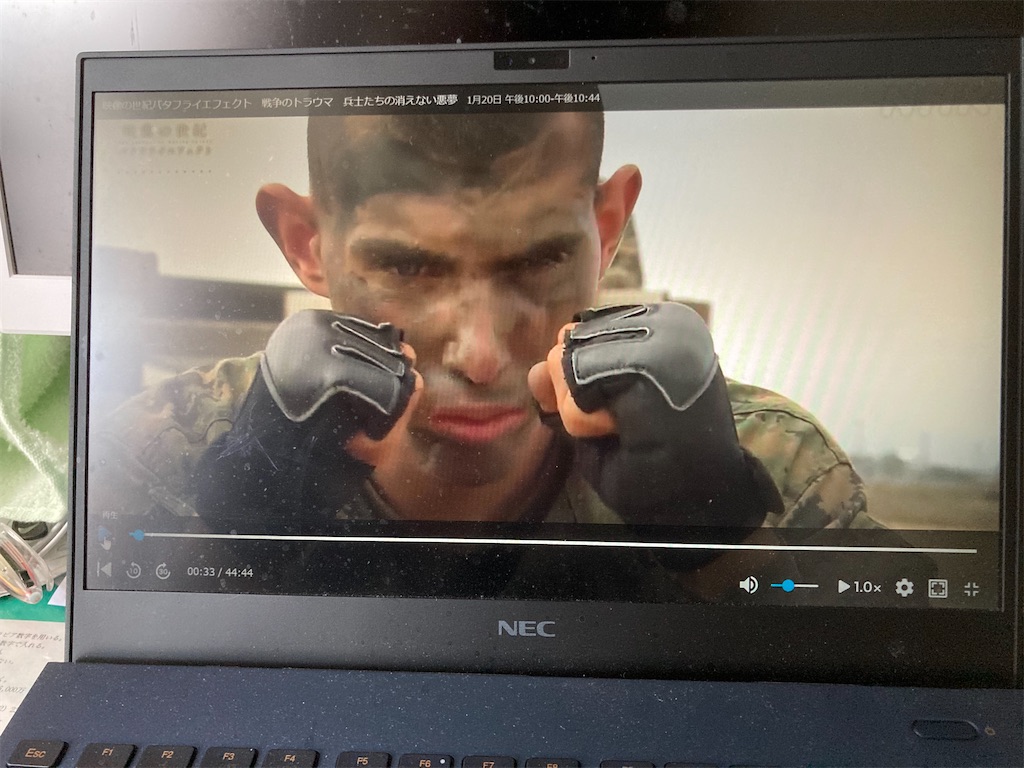
先日、「映像の世紀バタフライエフェクト 戦争のトラウマ 兵士たちの消えない悪夢」を視聴しました。その内容に強い衝撃を受け、改めて戦争がもたらす恐怖と残酷さ、そしてそれが兵士たちの心に刻む深い傷について考えさせられました。
トラウマの原因:戦場という極限状態
まず感じたのは、戦場が「極度の恐怖や生存の危機」と背中合わせの世界だということです。いつ自分が死ぬかもわからない上に、周囲では凄惨な光景が繰り返される。番組で映し出される銃撃や爆撃だけでなく、兵士たちが目撃する負傷者や市民への残酷な行為は、想像を絶するショックを与えます。そうした光景に長期的に晒されれば、誰しも心が深く傷ついてしまうのだろうと痛感しました。
さらに、近年注目されている「モラル・インジャリー(道徳的傷害)」という考え方も非常に印象的でした。要するに、自分の倫理観や価値観に反する行為を行う、あるいは目撃してしまうことで、深刻な罪悪感を抱いてしまう。たとえば、民間人を誤って殺してしまうとか、命令だからとはいえ加害行為に加担してしまうことが、のちのちまで兵士の心に重くのしかかる——そういう話を聞くと、「自分が本質的に人を殺したくないのに、殺さざるを得ない状況に追い込まれる」この苦しみこそが戦争の残酷さを際立たせているように思います。
「良心的兵役拒否」という視点
番組を観ながら、「良心的兵役拒否者」という存在についても考えました。確かに、宗教的・倫理的な理由で兵役を拒否する人はいますが、実際に戦場を経験していなければ、PTSD やモラル・インジャリーを負うことは少ないのではないかとも感じます。一方、元々は戦意を持って参戦した兵士であっても、あまりに悲惨な経験をするうちに後から「本当は戦いたくなかった」と気づく人もいるようです。つまり、「良心的兵役拒否者だから PTSD になる」のではなく、「生々しい戦場体験が、自分のモラルやアイデンティティを根底から揺るがす」ということなのだと、改めて理解しました。
最新の治療法やアプローチを見て感じたこと
PTSD の治療としては、認知行動療法(特にトラウマ焦点化型 CBT)や EMDR(眼球運動による脱感作と再処理法)、さらには道徳的傷害(モラル・インジャリー)に特化したカウンセリングや集団セラピーなど、さまざまな方法があると番組や資料で紹介されていました。とはいえ、こうした治療を受けられる人ばかりではないというのが現実です。仲間同士で支え合うピアサポートの大切さを説いていましたが、果たしてどれほどの兵士がそうした環境を手にできるのでしょうか。
戦場での体験がトラウマになる一因として、研究では脳やホルモンバランスにも着目しているそうです。慢性的なストレスが海馬を萎縮させ、フラッシュバックをよりコントロールしづらくしてしまうと聞くと、改めて「精神の問題」というのは、単なる気持ちの持ちようではなく、身体的・生物学的な問題でもあるのだと考えさせられます。
番組に登場した兵士のエピソードに思うこと
特に印象的だったのは、ベトナム戦争に従軍して 17 人を殺害した黒人兵士の話です。彼は戦後もずっと精神科の治療を受けていて、取材の 6 年後に自ら命を絶ったといいます。番組を観ていると、彼が受けた心の傷は、自分の行為を想像してしまう力から来ているのだと感じました。もし想像力が極端に欠如していたら、もっとあっさりと「戦争だから仕方なかった」と割り切れたのかもしれません。けれど、想像力が豊かな人ほど、自分の手で殺した相手やその家族の姿を思い浮かべてしまうのだろう……と思うと、胸が痛みました。
人を殺すことに抵抗がなくなる訓練を見て感じた矛盾
アメリカ軍の訓練施設を撮影した映像では、実際の戦場さながらにイラクの街並みを再現し、何度も何度もシュミレーションする場面が映されていました。そうすることで、人を殺すことへの抵抗感を薄れさせるというのですが、同時に「戦争からくるトラウマ」が深刻だという認識も持っているわけですよね。人間の心は簡単に訓練や薬でコントロールできるものではない一方で、軍は効率よく「殺せる兵士」を育てたい——まるで心と身体が引き裂かれていくような矛盾を感じます。
兵器やシミュレーション技術などはどんどん進歩しているのに、肝心の「人間の心」に対する向き合い方は大きく進歩しないまま。結果として、「戦争」という行為そのものの非合理さや残酷さがますます浮き彫りになっているように思えてなりません。
戦争が心を崩壊させる理由
私は、戦場に立つことで、人間が普段「当たり前」としている社会的ルールやモラルが否定されてしまうのだと思います。仲間と敵を分け、相手が人間でも殺さなければ自分が殺される——この単純な理屈の前に、それまで信じてきた秩序がいっさい意味をなさなくなる。まるでフィクションと現実の境界が曖昧になり、何が真実なのかわからなくなるのだろう、と番組を観ていて想像しました。
その結果、戦争から帰還しても、「もう何も信じられない」「何も美談やフィクションを描けない」という状態に陥る。トラウマを抱え、自殺に至る人も多いという悲劇——あの番組で映し出されていた兵士たちの姿が、その事実をはっきりと物語っているようでした。
私が感じたやるせなさ
あの放送を観て、自分自身は平和な環境で生きていても、どこか遠い場所では今も誰かが戦っていて、同じような苦しみを抱えているのだと改めて気付かされました。国のため、仲間のためと言いながらも、実際に戦場で「得をする」のはごく一部の権力者や裕福層であるという構造に、正直やりきれない怒りを感じます。兵士たちの心の傷を置き去りにして、世界は回り続けていく。そんな理不尽な現実を見れば見るほど、「もう人間に生まれ変わりたくない」とさえ思ってしまいます。
結論:戦争のトラウマと人間の脆さ
番組を通じて、戦争によって生まれる PTSD やモラル・インジャリー、そこからくる自殺などの悲劇は、想像以上に根が深い問題だと痛感しました。兵器や訓練のテクノロジーは進んでも、人間の心はそう簡単には変わらない。だからこそ兵士たちは心を壊し、長年苦しむのだと思います。
「何度も“殺せ”と声に出して言わせることで抵抗感を失わせる」という訓練がある一方で、私は自分の将来像を何度も声に出す“ポジティブ暗示”の話を思い出しました。言葉は、人の心を良くも悪くも変えてしまう力がある——そんな当たり前のようでいて恐ろしい真実を、改めて突きつけられた気がします。
結局、実際に戦争で負った心の傷は、当事者にならないとわからないのだと思います。兵士たちの映像を観ても、私はただ「これがどれほどつらいことなのか」を想像するしかできない。しかし、その「想像するしかできない」という距離感こそが、同じ悲劇を繰り返す遠因なのかもしれません。
いずれにせよ、今回の番組は、自分がいかに「戦争の悲惨さ」を理解していないのかを痛感させるものでした。平和への希求と同時に、人間という生き物が抱える醜さや愚かしさに、どうしようもない絶望を感じます。だからこそ、目を背けずに向き合わねばならない問題だとも思いますし、こうしたドキュメンタリーが世にあることをありがたいとすら感じました。
もう二度と人間に生まれ変わりたくない——そんな極端な思いが頭をよぎるほど、戦場という地獄は兵士の心を破壊し続けるのだと、改めて感じさせられた番組でした。

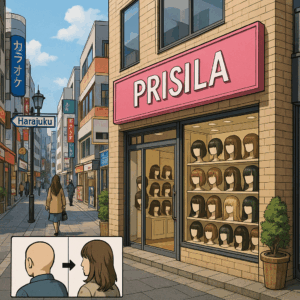
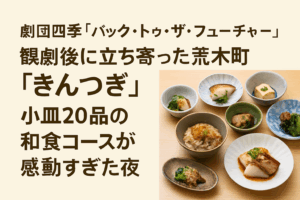

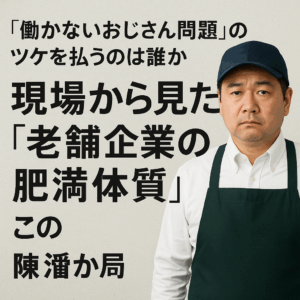
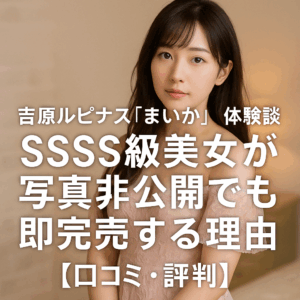

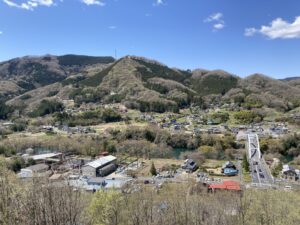

コメント