
AIのおすすめで『エターナル・サンシャイン』を鑑賞したものの、初見では筋書きやテーマが掴みにくく、何度も検索やAIへの質問を繰り返してようやく作品の狙いを理解した。物語の核となる「記憶を消去する」という設定は、主人公がヘッドギアを被りベッドに横たわるだけという子どもじみた描写に思え、もう少し科学的裏付けやリアリティがあれば感情移入しやすかっただろう。そうしたコメディタッチの演出が、作品本来のシリアスな側面をやや削いでしまっているという不満は残る。
しかし、その一方で、記憶が消されていく過程の映像表現や主人公ジョエルの心の揺れは本作の最大の魅力と言える。当初は「嫌な思い出を消して心の安寧を得たい」と願っていたジョエルが、途中で「クレメンタインとの大切な記憶は消したくない」と必死に抵抗する姿こそ、記憶がいかに私たちの存在を形作るかを痛感させる。星空を見上げるシーンで、あえて星自体ではなく二人の表情を中心に映す演出は、心情描写に徹したカメラワークであり、過去と現在、夢と現実が複雑に交錯することで、観客に「何が本当の時間か」を意識させなくなる瞬間さえ生み出している。
こうした時間や空間の揺らぎは、記憶という曖昧な領域を巧みに映像化する役割を果たしている。たとえば、ジョエルとクレメンタインが仲良く星を眺める場面から一転、クレメンタインが別の男性と星を見上げるシーンへ唐突に移行するなど、混乱を招きそうな構成によって“どれが実際に起こった出来事なのか”をあえて不透明にし、記憶そのものが持つ不確かさを観客に体感させている。
物語を象徴する「Eternal Sunshine of the Spotless Mind(汚れのない心に降り注ぐ永遠の陽光)」というフレーズは、アレクサンダー・ポープの詩から引用されている。傷一つない純粋な心でいることが、果たして真の幸福なのか――それとも、傷や失敗、痛みがあるからこそ人間は学び、喜びを噛みしめることができるのかという根源的な問いかけが、このタイトルに凝縮されている。映画の中では、少年時代のジョエルの記憶が回想され、母の目を盗んで机の下に隠れる無邪気さや、友人とのやりとりの中に潜む小さな残酷さなど、誰しもが経験してきた普遍的な“汚れ”や“痛み”が描かれる。それこそが、私たちを成長させる本質的な要素ではないか、という問題提起なのだ。
終盤、雪の降る中でジョエルとクレメンタインがふざけ合うシーンで物語は収束する。ここには「記憶を失ったとしても、また同じ相手を好きになるかもしれない」という運命論的なロマンチシズムと、「人生には決して純粋なものだけが存在するわけではなく、汚れも混じり合っているからこそ価値がある」というリアリズムが同居している。ドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』に出てくる“美”の概念のように、人間の心には聖なる理想と醜悪な欲望が混在しているからこそ複雑であり、それがゆえに美しいのだと本作は語りかける。
鑑賞後に抱く「これはコメディなのか、シリアスなのか」という違和感は、この映画がまさに“人生そのもの”を凝縮しているからかもしれない。笑いを含む軽妙さと、どうしようもなく重苦しい痛み――両方が不可分に存在する現実の写し絵を見せられることで、観る者は自身の記憶や過去の選択にも思いを巡らせることになる。結果として、本作が問いかけるのは「嫌な記憶を消して本当に幸せになれるのか?」「失敗や傷を負わずに得る平穏と、傷だらけでも得られる豊かさのどちらがより人間らしい幸福なのか?」という問いだ。すべての記憶が曖昧となり、あるいは美化され、時に痛烈な現実を突きつける中で、私たちは“自分自身を形作るものは何か”を改めて考えさせられる。
『エターナル・サンシャイン』は、記憶や愛の本質を問うだけでなく、人間の心が抱える矛盾や混在する感情の豊かさ、そしてその“取り扱いの難しさ”を見事に映し出した作品である。痛みと喜びの両面を受け入れることでしか得られないものがある――そのメッセージこそが、この映画の真髄なのだろう。

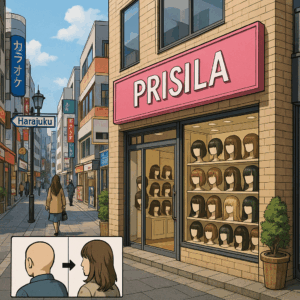
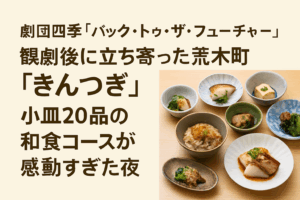
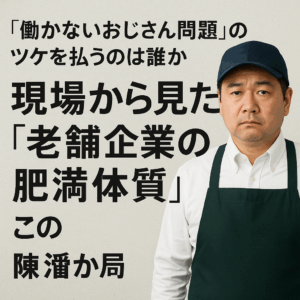
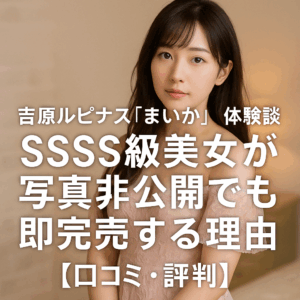

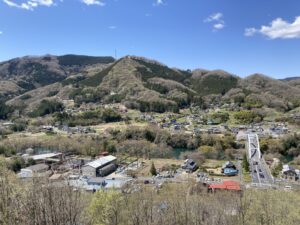


コメント